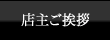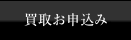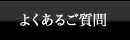明石国行
明石国行(あかしくにゆき)
- 指定:国宝
- 太刀 銘 国行 (号:明石国行)
- 日本美術刀剣保存協会(刀剣博物館)蔵
- 長さ 2尺5寸3分弱(76.6cm)
- 反り 1寸(3.03cm)
来国行は、来派の事実上の祖であり、その年代については、子と伝える二字国俊の弘安元年紀の作が存在することにより、ほぼ推定され正元(1259)・文応(1260)の頃が最盛期とされる。来国行は、現存する殆どが太刀で、短刀の遺例は寸延びて僅かに反りのついた島津家伝来のもの一口となっている。来国行の太刀姿は陰陽両様があるとされるが、陰の造込みの細身・小鋒の優しい姿のもの、陽の造込みの身幅広く豪壮で猪首鋒になったものがある。また他に身幅ほぼ尋常の手のものなどがある。来国行の作風は同国の先達、粟田口国安や綾小路定利の風に則った感があり、一段と刃幅を広く取り、さらに新味を加えたものといわれている。一般に刃取りは下半殊に腰の出入りのある乱れを見せ、上へは広直刃調に足を深く入れたものが多く見られ、大概のものには棟焼が見られる。直刃調の穏やかな刃取りでありながら棟焼を見せるところに異色ぶりがあり、これは二字国俊・来国俊・来国光・来国次に受け継がれている。また細身の手以外には棒樋を掻くものが多い。帽子の焼きは直ぐに小丸に返る温和しいものが通例であるが、横手の下辺りから金筋や砂流しが強くかかり、刃中に覇気を見せるものがある。
明石国行は、笠木反りの姿形や、よく錬れた鍛え肌、大出来の乱れでないにも拘わらず棟焼をみせているところ、乱れの逆がかる様子が備前や備中物などとは反対に頭が鋒の方に向き足先は茎の方に向けて下向きに入る特異な態など、作風様式論的には来派一般の特色が著しいが、さすがに気品が一段と高く泰然たる風情に来国行と指摘し得るものがある。腰元にある樋中三鈷柄附剣の浮彫は来国行のみならず鎌倉時代の諸工の中でも極めて珍しい例である。会心の出来映えに加え、ほぼ製作当初の状態で伝存することが貴重で、来国行中の白眉といわれている。来国行の国宝指定は明石国行のみである。藩政時代は播州明石藩主松平家に伝来した。
形状は、鎬造、庵棟、重ね厚く、身幅広め、元幅と先幅の開き少なく、笠木反り高く、踏張りつき、中鋒猪首風となる堂々たる体配である。鍛えは、板目に少しく流れ肌交じり、総じて約みごころ、肌目やや立ち、地沸微塵につき、地景入り、かねよく冴え、淡く沸映り現れる。刃文は、焼幅を広く取って直ぐ調に浅くのたれ、それに小丁字を主に角ばる刃や小互の目など交じり、小足・葉繁く入り、小沸よくつき、砂流し・金筋かかり、また刃縁には小模様の打のけや湯走りがかかり、匂口締まりごころによく冴え、随所に棟焼きを見せる。帽子は、のたれ込み大丸ぎみに僅かに返り、この付近一層あつく沸づき、盛んに掃きかける。彫物は表裏に棒樋、表は掻き流し、裏は掻き通し、ともに腰に三鈷柄附剣の浮彫がある。茎は生ぶ(雉子股風)、先極く浅い栗尻、鑢目切り、目釘孔三(中一忍孔)。
播磨国明石藩松平家は、天和2年(1682)、越前国大野より松平直明が六万石で入封し、松平氏が幕末まで在封する。直明の父直良は、徳川家康の次男:結城秀康(越前北庄六十八万石城主)の六男、直明は、家康の曾孫にあたる。八代藩主に、十一代将軍家斉の子:斉宣が就任し、このとき二万石を加増され八万石となっている。慶応4年、鳥羽伏見の戦いがはじまると、徳川御家門の明石藩は兵を京都へ急派した。しかし実戦にまにあわず砲弾を一発も発しなかったが、徳川荷担とみられ、新政府の山陽道鎮撫軍の攻撃をうけようとしていた。藩主:慶憲は、本家の越前福井藩老候慶永(春獄)の助けをかりて、危うく攻撃の手をまぬがれたのだった。その後明石藩兵は、新政府軍にしたがい、播磨・越後へ出兵した。
(参考文献:日本刀大百科事典より転載・引用・抜粋)
| (法量) | |
|---|---|
| 長さ | 2尺5寸3分弱(76.6cm) |
| 反り | 1寸(3.03cm) |
| 元幅 | 9分7厘(2.95cm) |
| 先幅 | 6分6厘(2.0cm) |
| 元重ね | 2分3厘(0.7cm) |
| 先重ね | 1分3厘(0.4cm) |
| 鋒長さ | 9分6厘(2.9cm) |
| 茎長さ | 6寸9分(20.8cm) |
| 茎反り | 1分3厘(0.4cm弱) |