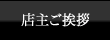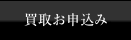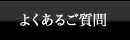日本刀のできるまで
玉鋼をはじめとする日本刀の材料は和鉄(鋼)といわれるもので、現在の、例えば新日鉄の溶鉱炉で造られる鉄(洋鋼)とは違います。この両者の違いは、和鉄が日本古来の製法で低温にてゆっくり還元されるのに対し、洋鋼は高熱処理により造られる鉄で、刀の鍛錬には適さない燐や硫黄の化合物を多く含んでいることです。
和鉄は砂鉄から作りますが、それは我々が想像する川砂鉄・砂砂鉄からではなく、山砂鉄からです。川砂鉄・浜砂鉄は採取料が少なくとても多くの鉄製品の原料にはなりえず、山を切り崩して取る山砂鉄に頼ります。昔より、備前(今の岡山県)は刀剣王国といわれ名工が数多く輩出していますが、それはそこで取れる赤目砂鉄と、それを還元するのに必要な山林が、中国地方の山の中に無尽蔵にあったからとされています。
砂鉄を数日間かけてタタラで吹いて低温還元した鉄塊の中には、少量の玉鋼と包丁鉄・ずく、などと呼ばれるそれぞれ品質の違う鉄が出てきます。この玉鋼が刀の原材料で、この優秀な鋼を使うことに日本刀の生命があるのです。しかし、玉鋼は多くの砂鉄からほんの少量しか採取できず、従って高価です。玉鋼だけで造れば素晴らしい刀が出来るわけでしょうがそうもいかず、玉鋼に包丁鉄などを混ぜて卸し鉄をつくり、それで刀を造ります。流派によってこの卸し鉄の混合の比率や卸し方が違い、地鉄の味わいが違ってくるのです。
平安・鎌倉の頃は、刀鍛冶自身もタタラを吹いて鉄をつくっていたこともあったようですが、室町期から江戸期になると、完全な分業体制が確立し、鉄は鉄屋さん、鍛冶屋は鍛冶屋さんというわけで、刀鍛冶自身が材料造りに腐心することはなかったようです。
しかし、玉鋼は少量しかとれず大変高価であったため、自然、腕前がよく金まわりのよい刀工に玉鋼も集まってしまい、ますます良工は名刀を作り上げた、ということもあるようです。
現代のタタラ操業は、明治以降、一般に鉄に対する要求が変わり、製造される鉄は洋式溶鉱炉の洋鉄一本槍になりました。他の鉄製品についてはこれでよいのですが、刀は洋鉄では造れません。たとえ造ってみても、地鉄・刃文に変化や潤いのない、ただ切るだけの鉄の棒になってしまいます。
ただ、辛うじて戦前島根の安来製鋼所で和鉄がほそぼそ造られておりましたので、その残りなどで現代刀匠は作刀しておりました。しかし、それでは、限りがあります。よって必要にせまられ、現代刀匠は刀だけでなく自家製鋼という鉄の製造にまで携わることになりました。時代が、江戸・室町をとび超え鎌倉の時代まで戻ってしまったわけです。
その現状を見かねて、(公)日本美術刀剣保存協会が昭和52年より、関係者各位の寄付をあおぎ、大きな規模で同じ安来に「タタラ操業」を開始いたしました。戦前の安来タタラの技術者が高齢ながら生存しており、その技術をなんとか今につなぎ、玉鋼の製造に努力をかたむけ、現代刀匠に「現代の玉鋼」を分与するようつとめております。
日本刀の特徴は、昔より言われるように「折れず、曲がらず、よく斬れる」です。しかし、この「折れず、曲がらず」は鉄にとって相反する性質です。曲がらないよう硬くすれば、一定以上の力が加わった時、カミソリの刃のようにポッキリ折れてしまいます。折れないために軟らかい鉄を使用すれば針金などのようにグニャグニャ曲がってしまいます。
そこで、いつごろからか、外側を硬い皮鉄で包み、中に柔らかい心鉄を入れるようになりました。これにより折れず曲がらず、加えて硬い皮鉄にさらに焼きを入れるので、よく斬れるという日本刀の最大の特徴が生まれました。
さて皮鉄は、刀鍛冶が玉鋼を加えた卸し鉄を何度も折り返し鍛錬します。たたくことによって不純物をたたき出すと共に、折り返すごとに鉄の層は倍々に増えていき、十回折り返すと1,024の層にまでなってしまいます。強度の強い鉄の層がそれだけ積みかさなるわけですからその強靱さはまさに計り知れなくなるわけです。
心鉄の方は、柔らかい鉄で、これも数回折り返し鍛錬します。この皮鉄と心鉄とうまく組み合わせて刀を造るわけですが、方法として、まくり・四方詰・本三枚・甲伏せ、などの造り方があります。
なお、皮鉄は玉鋼を使いますので高価です。そのため、心鉄にくらべ薄く造ることが多く、研ぎを多く経ると、皮鉄が段々なくなり心鉄が露出してくる時があります。無茶な研ぎは禁物です。
刀造りの順序としては、
1、日本刀の原料鉄の玉鋼を用います。
2、砕いた玉鋼及び卸し鉄を積み上げて沸かしにかける。
3、「積み沸かし」をするためアク(ワラ灰)をまぶしつける。
4、火床に材料の鉄をいれ、ふいごを吹いて火力を高める。これを「沸かす」という。
5、「積み沸かし」を経て赤熱した鋼塊は、火床から取りだして軽く叩いてならし「折り返し鍛錬」に移す。
6、「折返し鍛錬」で鉄質を錬る。
7、「沸かし延べ」。心鉄皮鉄の結合も済み刀形に延べられる。
8、「火づくり」。小槌で肉置き・棟の形や、また刃方をうすく、棟寄りを平らにして鎬をたて、ほぼ刀の原型をつくる。
9、ヘラで刀身全体に焼刃土を延ばした後、最も苦心を要する。「土取り(土置き)。」これで刃文がきまる。
10、「土置き」され、刀身全体に素焼きの土をすっぽりまとまったような姿を
11、燃えさかる火床の中にゆっくりと差し込み、右手で刀身を静かに火中で前後させる。やがて、刀身全体が赤らんでくる。
12、「焼き入れ」。平均に赤めた刀身を一気に水中(焼舟)に入れ冷却する。刀の出来はこの一瞬にかかっている。
13、簡単な鍛冶研ぎを加え、刀身をととのえていく。このあと茎にヤスリをかけ銘切りをする。