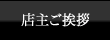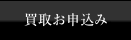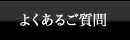居合刀買取
居合刀とは、居合いの練習用の刀のことで、奥州住人林崎甚助重信によって創始された居合い術は、敵から不意に切りつけられた時、いかにして長い刀を早く抜くか、という練習だった。したがって居合い刀には長い刀が用いられた。それを坐撃(いあい)太刀ともいう。幕府の講武書の教官:窪田清音は、身長五尺五寸(約166.65cm)の人ならば、四尺(約121.2cm)の刀まで抜けるという。
清音は腕の力を鍛えるため、ふだんの練習用には、刃長三尺二寸六分七厘(約90.0cm)、元幅一寸六分五厘(約5cm)、重ね六分六厘(約2cm)、柄や鐔を入れると、総重量二貫二百九十匁(約8.8kg)という豪刀を使っていた。しかし、門人たちには、三尺三寸(約100cm)を居合い練習刀の定寸、として教えていた。
その理由として、三尺三寸ならば、身幅は一寸一分(約3.3.cm)、反り一寸二分(約3.6cm)ぐらいあるから、普通の体格のものでも、遣いこなせると言っている。しかし、体格や力倆によって、二尺(約61cm)でも、四尺(約121cm)でもよい、と幅のある見方をしている。
実践においてはこれとは逆に、刀を短くして、抜き打ちに敵を倒す術が案出された。開祖:重信の三傑の一人:溝口八郎右衛門氏の、いわゆる関口流では、長い刀をつかう正統派を大関口、抜き打ちの早業を小関口と呼んだ。重信の三傑の一人:田宮平兵衛業延の流れをくむ田宮派には、「せばみにて勝を取べき長刀 みじかき刀利はうすき哉」という居合い歌があるとおり、やはり長い刀が好まれた。しかし古人は、外見に走って長い刀を用ゆべからず、片手で自由に操れる刀を選ぶべし、と教えている。なお、刃筋が傾かないためには、ある程度反りの強いほうがよい。切りおろした際、樋のある刀は刃音が高いので、好む人もある。
居合い柄とは、居合い術の練習のさい用いる刀の鞘で、柄下地つまり柄木は掌の形に合わせて、差し表に丸味を持たせ、裏はやや平たく削る。縁頭もそれに合致するような形になる。堅牢を要するので、柄頭の金具を深くしたものもある。なお、安価であることも必要なため、鮫皮は柄の両端には角形のものを用いるが、他は細長く切ったものを用いる。細長くては動くので、柄下地を切り込んで、そこに嵌め込む。柄糸は傷みやすいので、巻き上げてから漆をかけた、いわゆる塗り柄にすることもある。
居合い抜きとは、大道芸として見せ物にした居合い術のことで、越中富山の売薬・反魂丹売りの松井源左衛門(源水)が、延宝(1673)、天和(1681)のころ江戸に出て、浅草で客集めにやったのが始まりといわれる。享保(1716)の初めころ、源左衛門は黒塗りの膳を高く積みあげ、その上で長い刀を抜いてみせた。享保十一年(1726)十一月十三日、将軍:家重の上覧に供したのは、曲独楽と枕の曲(椀返し)だけで、居合い抜きは遠慮したようである。明治になってから、十六代源左衛門が歯磨き売りの宣伝に、居合い抜きをやっていたが、晩年は衰退した。
幕末に有名だったのは、浅草蔵前居住で歯磨き売りの長井兵助だった。これも文政(1818)のころ、将軍:家斉の上覧に供する栄誉を荷なった。兵助は三方を高く積みあげた上で演じたが、口上が長くて容易に抜かなかったという。松井・長井両家のほかに、安永(1772)のころ出た茗荷屋門次郎も、両国広小路で歯磨き売りや歯抜きの宣伝に使った。ただし歯抜きはサクラを使ったそうである。居合い抜きはインチキもあった。文化(1804)のころ下谷において、蓋をした風呂桶のなかで、風呂の深さほどの刀を抜いて見せるものがいた。が、それは蓋を取る瞬間に抜いたもので、あまりに素早いため民衆に分からなかっただけという。今次の終戦後においても、荒木又右衛門の十代目を名乗る同名の人が、居合い抜きを進駐軍相手のショーにしていた。