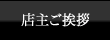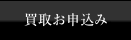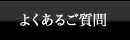太刀買取
・刀剣の総称のことであり、太刀の語源は「断チ」で、敵を断ち切る刃物の義といわれている。大刀(たいとう)の変化したものとの説は採らない。長さに関係ない例として、太政大臣が皇太子に贈った「横刀(たち)」は、長さ一尺四寸七分(約44.5cm)しかなかった。短刀や刺刀は古くはノダチともよんでいる。
・長くて、片刃の刀剣で、豊前の神息が利剣を縦に二分して、太刀を作ったとか、不動明王の利剣を二分したとかいうのは後世の付会である。太刀の長さは星の27倍に合わせて、二尺七寸(約81.8cm)が正式、とする説は、宿曜道つまりインド起源の星占いや、漢の高祖の三尺の剣は周尺、これを日本の曲尺になおせば、二尺七寸になる、という計算からである。江戸期には二尺六寸(約78.8cm)くらいより長いものを、太刀とよんでいた。
・鎌倉時代後期の正応(1288)以前の長い刀のことで、正応以前の刀は身幅が狭かったが、正応のころ相州に正宗が出て、身幅の広い刀を作り始めた、と解釈し、戦国末期から正応以前を太刀、それ以後を刀と区別するようなり、本阿弥家もこの説に従って、折紙などを書いた。
・銘が佩き表に切ってある長い刀のことで、これは鑑定上の定義であるが、古い備中の青獲物は例外で、太刀でありながら、銘を佩き裏に切った。なお、新刀の肥前忠吉などは、普通の打ち刀として作ったと思えるものに佩き表、つまり差し裏に銘を切ったものがある。
・太刀拵えのついた長い刀のことで、刃が下に向くようにして、鞘につけた帯取りで、左腰に結びつける、つまり佩くようになった拵えの付いた長い刀を指す。これに儀仗・兵仗の別があり、それぞれに多くの種類がある。
・大名の刀のことで、室町期、天皇の刀を御剣、将軍の刀を御剣または御佩刀(みはかし)といった。一方、それに対して大名たちが持った刀はタチといった。
大太刀とは、通常のもよりも寸法が長大な太刀のことで、中取り・大長刀ともいう。これは儀仗・兵仗の二種あって、儀仗は古くからあった。
・儀仗 伊勢神宮の神宝である玉纏大刀や須我利大刀は、刃長三尺五寸(約106.1cm)、外宮の大刀は刃長三尺九寸(約118.2cm)もあった。武烈天皇の歌に、「飫裒陀㨖嗚多黎播枳(オホダチヲタレハキ)」とある大太刀も、伊勢神宮にある神宝のような飾り太刀のことであろう、という。後世になると、神社における奉納用のために大太刀が作られるようになった。越後一の宮の弥彦神社に、応永21年(1415)、志駄定重が奉納した、家盛の太刀(国宝)は、刃長七寸二分七分(約220.3cm)、宝徳2年(1450)、日向国妻(西都市)の都万神社に奉納された則次ら五人の鍛冶たちの合作刀は、身長八尺一寸二分(約246.0cm)、熊本の本妙寺に天保5年(1834)、万宝子国幸らが合作で奉納した大太刀は、刃長一丈七寸(約324.2cm)となる。
・兵仗 古墳からの出土刀に、まれに五尺(約151.5cm)を超えるものがあるから、古くから大男たちは大太刀を用いたとみえる。軍記物における大太刀の初見は、「保元物語」における鎮西八郎為朝の三尺五寸(約106.1cm)である。「源平盛衰記」になると、さらに寸が伸びて、畠山重忠は三尺九寸(約118.2cm)、綴太郎は四尺八寸(約145.4cm)の太刀を佩く。「太平記」になると、初めは五尺三寸(約160.6cm)が、「其の頃曽てなかりし」大太刀だったが、のちには大高重成の五尺六寸(約169.7cm)はおろか、福間三郎の七尺三寸(約221.2cm)が登場してくる。これは「太平記」の誇張とばかりは考えられない。
「応仁記」においては武田基綱と一宮勝梅、「国府台合戦記」では里見義弘の太刀も七尺三寸(約221.2cm)とあり、さらに「官地論」では、富樫政親に藤島友重作、九尺三寸(約281.8cm)の大太刀を持たせている。これほどでなくとも、かなり長大な太刀が実用されていたことは、「七十一番歌合」に、鐔が肩までくる大太刀を杖にした図があり、「清水寺縁起」・前田家蔵「祭礼草子」・「玉石雑誌続編」などにも、鐔より先が身長ほどもある大太刀の図が、描かれていることでも実証される。
室町時代にはこういう大太刀を、従者に持たせることは、一種の見えでもあった。しかし古くは武将自身が、背に斜めに負って出陣したもので、「一谷合戦絵巻」にも、そのように描かれている。大太刀を背に負ったままでは抜けない。肩からおろして刀を抜き、鞘だけをまた背に負うか、または負ったまま従者に抜かせるかした。
大太刀遣いは、大太刀の遣い手で、謡曲「烏帽子折」に、「熊坂も大太刀使の曲者なれば」とある。幕末、尾張藩には、玄流といって、石来清次朗四迷を祖とする大太刀遣いの流派があった。
背負い太刀とは、背に負っていく長大な太刀のことで、「一の谷合戦絵巻」に、身の丈より長い太刀を、背に負った騎馬武者の画がある。
長太刀は、太刀に長い柄をつけたもののことで、室町期になって出現したもので、野太刀長巻きの太刀・長巻き・中巻きの太刀・中巻きともいった。和寇もこれを携行したので、中国では大制とよんだ。刃の長さは二~三尺(約60.6~90.9cm)で、柄の長さは持ち手の耳から地面までもあった。柄を滑り止めとして、紐で片巻きにしたので、長巻きの太刀とも、それを略して単に長巻きとも呼んだ。戦戦場では人馬の足を払い倒すのに用いたので、上杉家では「馬の脚払い」とも呼んだ。
鞘のないものは薙刀のように、手に携えたが、鞘のあるものは、帯をつけて背中に、斜めに背負った。江戸期になると、長太刀・長巻きの操法を専門とする流派が生まれた。堀部安兵衛は吉良邸討ち入りのさい、堀内流の長太刀を使った。刃の長さは二尺三~五寸(約69.7~75.8cm)、総長八尺(約242.4cm)あった。山浦清麿のパトロンであった窪田清音は、長巻き遣いの師範で、「長巻剣法伝授」「長巻考」「長巻図式」などの著書もある。
小太刀(こだち)は、短い太刀のことで、佩き添えの太刀・脇差の太刀・小さき太刀ともいった。長さの規定はないが、ただ大太刀や大薙刀に比較して、短いものをいう。弁慶の太刀に対する牛若丸の小太刀も、平家の大薙刀に対する義経方の美尾屋十朗の小太刀も、比較してのことである。三尺一寸(約93.9cm)の大薙刀を持った大内義弘が、小林上野守の二尺八寸(約84.8cm)の太刀を、小太刀と見なしたのも、やはり比較してのことである。
「太平記」の時代には、五~六尺(約1.5~1.8m)の大太刀が現れたので、普通の太刀でもそれと同時に佩いていれば、小太刀と呼ばれた。大太刀が使われなくなると、二尺(約60.6cm)前後から一尺七~八寸(約51.5~54.5cm)の太刀拵えのものを小太刀と呼んだ。江戸期になると武術の流派によっては、長さを規定したものもあった。疋田流において小太刀は柄ともに二尺三寸(約69.7cm)、柄前の長さ五寸(約15.2cm)と定めたごときである。
刀剣界の述語としては、二尺(約6.0.6cm)前後から、一尺七~八寸(約51.5~54.5cm)くらいまでの古刀で、銘が佩き表に切ってあるものをいう。
剣(たち)は、飾剣・細剣・野剣・蒔絵剣・螺鈿剣などの場合、「剣」はタチとよむ。「万葉集」でも小剣と書いてオダチとよむ、なお、宝剣をタチという、との説もある。
神楽歌の題名のことで、歌詞は「白銀の目貫の太刀をさげ佩きて、奈良の都を練るは誰が子ぞ。石の上ふるや男の太刀もがな、組の緒垂でて宮路通はん」、と「拾遣和歌集」の歌をうたうもの。
大刀(たち)は、奈良期より以前の文献では、タチを大刀と書く。草那芸之大刀・物部目連の大刀・金銅荘唐大刀・玉纏大刀などがその例である。
横刀(たち)は、奈良朝以前の文献におけるタチの宛て字で、横刀之手上・弓矢及横刀・玉纏横刀などがその例である。中国で横刀といえば、兵士の佩く刀で、名称はすでに隋の頃からあった。多くは刀ヲ横タツとよむ。