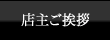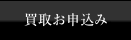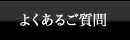刀剣鑑定の歴史
刀剣鑑定の歴史は、初めは実用上からの良否、つまり切れるか切れないかの鑑別だけだった。「大宝令」によって刀工名や製作年月を刻むよう規定されたのも、ナマガネで造った刀を、ハガネで造った刀と偽って売るものがいた。ナマガネで造っては切れないのが当然だから、切れる刀を造らせるための規定だった。源三位頼政は藤原信頼が石を切って、曲げてしまった太刀を見て、これは伊勢神宮にあった五剣のうちの第三の剣、と鑑定するほどの目利きだった。
そのとき「作人ニテ剣体ヲ知ル」と言っているのは、当時すでに作者によって刀の特徴を見分ける法が、行われていたことを示すものである。後鳥羽上皇は「剣などを御覧じ知ることさえ、道のものにもやや立ち勝りて、かしこくおはしま」したという。「道のもの」とあるから、当時すでに鑑定家と目される人がいたことになる。
仁治2年(1241)といえば、北条泰時の晩年であるが、そのころ金窪行親は「剣刀ヲ見ル事、既ニ彼ノ通ノ如シ」、という。この「通」もいわゆる鑑定家のことである。金窪行親も関係したに違いないが、北条泰時のとき、天下の名工を「平泰時被評定分」として、11名選別している。そののちも、北条時頼のとき22工、北条貞時のとき22工を追加し、さらに城禅門、つまり安達泰盛が5工を追加している。すると、泰盛は当時、鑑定の大家だったことになる。
北条貞時の晩年、正安(1299)のころには、刀剣書も編術されていた。著者は不明であるが、相当の大家がいたはずである。正和2年(1313)には「注進物」の選定が行われた。これは全国に令して、切れ味の優れた刀を注進せしめたもので、60工がその選に入っている。そのときの選定委員長は名越遠江入道崇喜だったようだから、これも目利きの大家だったことになる。北条高時が執権になった正和5年(1316)にも、刀剣書が編まれているが、それも著者不詳である。
吉野期の初頭、本阿弥家の初祖:妙本は足利尊氏に仕えた、というが、妙本の身許については、五条高長の兄とする説と、五条為守の兄とする説とがある。いずれも年代的に合わないので、高長の晩年の庶子とする憶説も行われている。そのほか、相州の松田氏の一族で、足利尊氏に従って上洛したという説もある。
本阿弥家六代目の本光とほとんど同時代の相州正宗は、諸国を歴遊して「廻明記」という本を作った、という伝説がある。それが真実なら正宗は鑑定の大家でもあったはずである。
正宗の孫弟子にあたる相州秋広は、25か国の押形を作った、というから、これも真実ならば大家だったはずであるが、いずれも後世の附会であろう。吉野末期、永徳(1381)ごろの喜阿弥は実在の大家だった。「喜阿本」と呼ばれる刀剣書を残している。当時、京都の「七条道場」に鑑定の大家がいて、喜阿弥はそれから相伝を受けたようである。同じころの斎藤弾正忠は、相州秋広より伝授をうけた、という。美濃の斎藤家の一族に違いないが、身許不明である。
室町期になると、喜阿弥の系統であろうが、能阿弥真能の活躍が目をひく。能阿弥は連歌師・画家としても名高く、かつ唐物奉行を勤めたほど、工芸品の鑑識にもたけていたので、いわゆる「能阿弥本」を書いた。これは本格的な刀剣書として、最初のものである。これに加筆増補した田使行豊も、大家の一人だったはずである。同じころ、江州箕浦備中入道も熱心な研究家だった。美濃においては、斎藤弾正忠から教えをうけた、宇都宮三河入道が出藍の誉たかかった。
足利将軍義満の命によって、「可然物(しかるべきもの)」や「新作物」を選定したり、「宇都宮本」と呼ばれている刀剣書を遺したりしている。三河入道から木本美作守宗剛・斎藤左京亮利英をへて、長井越中守利安へと、宇都宮流の鑑定術は美濃の地に栄えた。そして開いた花が、斎藤利安著「往昔抄」だった。その系統は尾張に伝わり、いわゆる竹屋流目利きとなって、江戸期まで続いた。
応仁(1467)の乱のころ、赤松下野入道政秀も大家として著聞していた。やはり宇都宮の流れを汲んだ人であろう。阿波の名族:三好下野入道は、斎藤左京亮利英に学んだ、というから、やはり宇都宮流である。下野入道から細くぁ幽斎へ、さらに建部内匠頭光重へと伝わった宇都宮の流れも、光重が早世したため、あとは聞こえるところがない。なお、下野入道から松永久秀へも伝えられたが、久秀も織田信長に滅されたので、目利きの流れも絶えた。
以上の宇都宮流のほかに、美濃には長谷川忠右衛門という武家目利きの家があった。鍛冶系図をつくり、それに年代付けし、さらに押形本を残した功績は大きい。長谷川流の目利きとして、武将のあいだにも人気があった。上杉家の有名な直江山城守兼続の祖父にあたる大和守景綱も、目利きだった。そのほか、地方には武家目利きが相当いたようである。「阿弥目利き」、つまり時宗の僧籍にある目利きとしては、前記の喜阿弥や能阿弥のあと、昌阿弥・重阿弥・金阿弥・敬阿弥など、数名の同朋が、室町前期に活躍している。
桃山期になると、本阿弥家が豊臣秀吉の信任をえて、大いに勢力を伸ばしたが、それでもなお武家目利きとして、細川幽斎や長谷川忠右衛門、研屋目利きとして竹屋などが、隠然たる勢力をもっていた。江戸初期になると、本阿弥家は徳川家の御用目利きとなり、刀剣界に君臨するに至った。その他の勢力、つまり長谷川家や竹屋家のほか、木屋が徳川家の御用研師となり、いずれも伝書を発行し、大いに貢献するところがあった。木屋の女聟にあたる各野家からは江戸中期、莚上庵寿見(「享保午記」の著者)がでて、研屋目利として名をあげた。
同じころ江戸の神田白竜子(「新刃銘盡」の著者)、土屋家の阿佐見六郎兵衛らも有名だった。江戸末期になると、片桐石見守貞芳のような大名をはじめとして、旗本の土屋温直(「土屋押形」の著者)・窪田清音(「鍛記余論」などの著者)・山本平八郎・隠岐五郎太夫やその弟の十郎・旗本西郷家の松本無用・西丸坊主の高田久与らがいた。
藩臣としては、川越藩の鎌田魚妙(「新刀弁疑」などのの著者)・研師の浅岡安親、喜三郎の父子・土浦藩の荒木一滴斎(「新刀弁惑録」の著者)・浜松藩の柘植方理(「古今鍛冶備考」などの著者)・名古屋藩の矢田作十郎・松江藩の新宮小源次(「新宮押形集」の著者)・讃岐藩の細谷通寛(「刀剣雑話」の著者)・高知藩の服部政久(「刀剣問答録」の著者)・小倉藩の研師:岡本故藤四郎・熊本藩の松村昌直(「刀剣或問」の著者)・同沼田直宗(「刀剣疑解」などの著者)・薩摩藩の家村忠蔵らがいた。
そのほか、大坂与力の寺田治左衛門・処士の箕浦吉隆(「新刀賞鍳余録」の著者)・京都の社司:仰木伊織(「古刀銘盡大全」の著者)・研師の今村幸政(「新刀一覧」の著者)らの名があげられる。
本阿弥家では、豊臣・徳川両家に仕えた光徳のあとは、光室・光温・光常と嫡流が続いたほか、分家の光悦という偉人がでた。その孫の光甫も有名だった。同じ分家の加賀本阿弥、つまり加賀前田家お抱えの光山は、いわゆる「光山押形」の著者として知られ、その曽孫にあたる芍薬亭長根は、「校正古刀銘鑑」を著したほか、狂歌・戯作者として著聞していた。本阿弥家は本家分家あわせて12軒あって、折紙を出せるのは本家だけだったが、審査は十二家の合議制になっていた。したがって光忠まで、つまり江戸前期までの鑑定は、今日も妥当と是認されているが、その後特に田沼時代のものは、「田沼折紙」と呼ばれ、信用がない。幕末になっても、その信用は回復せず、かえって武家や研師の目利きに信用が厚かった。
明治維新になると、新政府は宮内省調度課に御剣掛を設けた。それらの合議制によって鑑定書を発行し、各個人の発行することを禁止した。しかし、その審査制度は一年ぐらいで廃止されたので、本阿弥平十郎・忠敬・長識・徳太郎らが、それぞれ鑑定家として独立した。しかし、その鑑定は合議制でなかったから、権威のないものとなった。廃刀令の発布により無用の長物視されていた日本刀も、日清戦役の勃発によって、その実用性を見直され、やがて愛刀熱も燃え上がってきた。
そこで明治33年、中央刀剣会が設立され、今村長賀や別役成義らが審査会を主宰した。審査員は刀剣12名、刀装具8名で、それらの合議制で、かつ厳格だったので、その鑑定証状は大いに権威あるものとされた。明治43年、高瀬羽皐によって創刊された雑誌「刀剣と歴史」を機関誌として、刀剣保存会が大正元年に結成され、ここでも合議制の鑑定が行われ、現在に及んでいる。
大正時代になると、なお本阿弥家として琳雅・天籟(「刀剣鑑定秘訣」の著者)・親善らがいた。これら死去のあとは、「水戸本阿弥」を継いだ本阿弥光遜(「日本刀」の著者)が東の横綱、大阪の杉原祥造(「長曽弥虎徹の研究」の著者)が、西の横綱として活躍した。昭和時代になると、戦前には東京に本阿弥光遜氏のほか、川口陟・藤代義雄の両氏、大阪の加島勲氏、広島の大村邦太郎氏が登場し、いずれも個人名で鑑定書を発行していた。
戦後になると、日本美術刀剣保存協会・日本刀剣保存会・刀苑社・日本春霞刀剣会など、いずれも合議制によって鑑定を始めた。ただし刀苑社は昭和53年、主幹:村上孝介氏、春霞刀剣会は平成元年、主幹:犬塚徳太郎氏の逝去により廃止した。