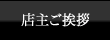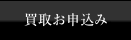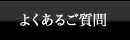南海太郎朝尊
南海太郎朝尊(なんかいたろうちょうそん)
- 位列:新々刀上作
- 国:山城国(京都府-南部)
- 時代:江戸時代後期 天保頃 1830-1843頃
朝尊の家系
森岡南海太郎朝尊は著書を三冊も書くほど、好学の士だったので、森岡氏系図も作っている。と言っても自作ではなく、いわゆる系図家に依頼したものに違いないが、それによると、朝尊の家は尊良親王に発するという。
尊良親王は後醍醐天皇の第一皇子である。いわゆる元弘(1331)の乱のさい、楠正成とともに赤坂城にこもり、関東勢を悩ましたかどにより、北条高時から土佐(高知県)の幡多へ流された。元弘2年(1332)から同3年(1333)まで配所にいて、のち京都に帰還された。しかし足利尊氏の反逆により、再び剣を掲げて関東から越前(福井県)へ転戦し、ついに延元2年(1337)3月6日、金崎城において自害された。時に御年27。
森岡氏系図によれば、秦氏、つまり長曽我部の時代、大禄をはんで朝倉村(高知市内)にいたが、天正(1573)年中、朝忠というものが黒岩村(高岡郡佐川町)に移り、子孫は世々、鍛冶を営んでいた。そして十一代目が朝尊であるという(『土佐偉人伝』)。朝尊もみずから自署『新刀銘集録』のなかに、「尊良親王十七代ノ孫ナリ」、宣言している。ところが、初期の銘には藤原姓を切ったものがある。それについて朝尊は、「文政・天保ノ頃、希ニ藤原ト打事有ハ、藤氏に交りて打ちタル事アリ。雖然、藤氏ニアラズ」
と弁解している(『新刀銘集録』)。しかし、それは森岡氏系図をつくる以前のもので、作ってから以後は、「尊良親王十七代ノ孫」になったので、藤原姓は使えなくなった、というのが真相であろう。
森岡家の墓地は、二ツ野の入口に近い大の城にある。山裾を切りひらいて造ったもので、人家より一段高くなっている。墓地を抱いた雑木林の木の間から、かつての鍛冶場がマッチ箱のように覗いている。現存する墓碑のうち最古のものは、13代:五郎兵衛のものである。
宝暦九己卯年(1759) 釈森岡五郎兵衛墓 正月十九日
14代の墓も現存する。
天明八年(1788)森岡清五右衛門 申三月六日
15代は父に先立って没している。
天明七丁未(1787)六月十四日 釈夏月信士霊 森岡長作幸蔵善右衛門父
15代の長男:幸蔵の系統が嫡流であるが、刀鍛冶でないので省略する。
15代の次男:善右衛門は独立して、いわゆる分家16代となった。ただし大鋸鍛冶で、まだ刀工ではなかった。
天保十亥(1839)八月四日 行年七十三 釈誠覚武栄信士霊位 森岡善右衛門 才次・朝尊・文平実父
この墓碑の側面に、妻かなの行年が刻まれている。つまり朝尊の慈母であるが、その没年の誌されていないのは惜しい。
善右衛門の長男、つまり17代を才次という。92の長寿を保っている。
明治廿六年(1893)七月廿八日 森岡才次墓 行年九十二歳
17代の長男は刀工ではなかったが、次男の良吾は叔父:朝尊について、造刀の術を学んだ。通称をはじめ亦次郎、中ごろ兵庫といい、刀銘を朝国と切った。
明治丗四年(1901)7月7日 森岡良吾墓 行年七十六歳
これの側面には、朝国の妻トラの没年が刻まれている。
大正九年(1920)七月十五日 森岡良吾妻 行年九十二歳 トラ
16代:善右衛門には、既述の長男:才次のほか、次男:朝尊、三男:文平など三人の男児と一女があった。末弟の文平は明治23年(1890)3月30日、76歳で亡くなった。朝尊とは8ツ違いだったことになる。ただし刀工ではなかった。
15代:長作の弟:権七は分家して、同郡佐川に移住した。それで墓地も同地の春日山(向かい山)にある。この系統から、朝尊に感化されて数人の刀鍛冶が生まれた。大正の森岡正吉もその一人であるが、京都居住ではない。
朝尊の活躍
朝尊は姓を森岡、通称を友之助または朝之助、のち孝之助と改めた。刀銘は友尊、のちと改めた。なお友高とも書くが、いずれもトモタカとよむ。ただし、朝尊はのちチヤウソンと音読するようになった。みずから刀銘に、「ちやうそんつくる」、と仮名書きしたものがある。「号」ははじめ雲匂子、のち南海太郎と称した。匂は和製文字であって、音読できないわけだから、雲匂子をなんと訓んでいたか、匂は韵の省画・匂よりでた字とされているから、強いて音読すれば、インと発音するほかない。
南海太郎のほうは、恐らく画僧の名:南海より採ったものであろう。南海はもと山城の産だったが、5歳のとき、朝尊の誕生地から4キロぐらいしか離れていない佐川町の音源寺にやってきた。のち同寺の法灯をつぎ、後水尾天皇から紫衣を授けられた。貞享元年(1684)示寂した高僧であるが、詩文をよくし、また画に巧みであった(『土佐偉人伝』)。
それで朝尊はその詩や画を見て、それにあやかるため、南海太郎という号を思い付いたのであろう。生誕の地は土佐国高岡郡黒岩村二ツ野三十一番屋敷(佐川町)だった。ここは現在でも、土佐加茂駅と西佐川駅の中間から、北へ山越えして行かねばならぬほどの僻地であるが、応永(1394)のころ、片岡左衛門尉直綱という関東武士がここに下り、土着したので、一名、片岡とも呼ばれていた。明治の実業家、片岡直輝・直温の兄弟は、直綱の後裔といわれている。
朝尊がココの声をあげた三十一番地屋敷は、うしろに山を負い、前に山あいの田圃を見おろす景勝の地である。朝尊の兄の嫡孫にあたる森岡亀太郎は、戦前にはその田圃を越した向かい側の山裾、つまり三十八番屋敷に移っていたが、鍛冶場だけは昔のまま、朝尊誕生地の崖下に保存されていた。煤けた梁、よごれた柱、1つとして追憶の情をそそらぬものはなかった。
朝尊は前述のとおり、善右衛門の三男として、ココの声をあげた。父が大鋸鍛冶だったので、それの鍛法は子供のときから仕込まれたが、天性、刀が好きだったとみえ、自己流で短刀など作りはじめた。生来、才気があって、かつ器用だったので、素人の慰作とはとうてい見えないほどの出来ばえであった。そのころ淬刃に用いた清水は、生花の裏山の背後、聖神の裏手に今もある。朝尊が後年、自著『刀剣行五論』に、
「水、清浄而強く、剣を造るには地より出づるを用ふる也」
と述べているとおり、朝尊が用いた淬刃水は、岩間からしみ出る真清水であって、それが下に溜まって、小さな池になっている。今は汲む人もないので、水草の生えるに任せている。傍の石のうえに、朝尊が建てた「剣井碑」がある。碑文を読もうとして近づくと、苔蒸した碑面を、沢蟹があわてて駈けおりる。その足音さえ聞こえるほど、四辺は静寂そのものである。
淬此清洌鋒芒絶倫(此ノ清洌ニ淬ゲバ鋒芒ハ絶倫)
立石表徳永鎮水神(石ヲ立テ徳ヲ表シ永ク水神ヲ鎮ム)
伊藤徳裕題
剣井 ふりすすききたふ剣のそこしみずやほよろつ代のすえにすむらむ 春樹
汲そむる人の心のそこふかき剣の清水千代に澄むらむ 道雄
伊藤徳裕は蘭林と号した儒臣で、土佐藩老:深尾氏に仕えた。文武二道にすぐれ、門人千人を超えた。後年の田中光顕伯爵もそのうちの一人だった。明治28年(1895)没、81歳(『土佐偉人伝』)。
道雄とは誰か、明かではないが、恐らく敷島の道にいそしんだ土佐藩士であろう。
さて、この「剣井」でやいた刀は、たいへん評判がよかった。それに気をよくした朝尊は、ついに刀鍛冶になる決心をした。
「刀鍛冶を正式に修行するため、京都に行ってくるぞ」
妻は、今から京都に修行など、とんでもない、と猛然に反対した。妻の両親も娘の味方となり、引き止めにかかった。しかし朝尊の決意は固かった。ついに妻を離別して上京した。
「友之助さんはよく決心した。やはり男だ」
世人はそういって褒めそやし美談としたという(『土佐遺聞録』『土佐偉人伝』)。
しかし、出郷の動機として、土佐藩がよそ者の左行秀を藩工にしたのを怒り、郷里をとび出した、という説がある(新刀古刀大鑑)。が、それは年代的にみて無理がある。
①朝尊が雄志をいだいて上京したのは、自著『新刀銘集録』に「文政中」と書いている。仮りに文政の末年(1830)としても、左行秀はまだ18歳でしかなっていなかった。明治20年(1887)、75歳で永眠しているからである(行秀墓碑)。18歳で藩工採用は無理である。
②左行秀がはじめて土佐の幡多郡入野にやってきたのは、弘化3年(1846)、つまり朝尊の上京より十数年後のことで、しかも藩工採用はそれよりまだ後だった(『土佐剣工録』)。
③行秀の藩工採用は、旧土佐藩士で、明治の愛鐔家として知られた秋山久作によれば、安政2年(1855)の大地震の後だったという(『新刀古刀大鑑』)。すると、朝尊の上京より20数年後のこととなるから、朝尊の上洛とはまったく関係がないことになる。
上洛後、どうしたか、まず日本鍛冶宗匠の伊賀守金道に入門した(『土佐剣工伝』)。朝尊みずからは、師事した刀工の名をあげていないが、のち金道の代作や後見をした、というから、伊賀守入門説は肯定してよろしい。
なお、江戸にくだり、新々刀の開祖:水心子正秀に入門した、ともいう。すると、朝尊の上洛は水心子の没年、つまり文政8年(1825)より以前ということになる。土佐に伝わった話であろうが、水心子に入門したとき、よほど自信があったと見え、
「わたしの刀は決して折れません」
と口走ってしまった。では、見せてご覧、ということになり、水心子は、朝尊のさし出した刀を一見したあと、
「これは折れますぞ」
と、自信たっぷりに言ってのけた。自信と自信が正面衝突した結果、
「では、折れるか折れないか、百疋賭けよう」
と言うところまで発展してしまった。その翌朝、折り試しをやったところ、水心子のいうとおり、ポッキリ折れたので、朝尊は面目玉を踏みつぶされた上、掛金百疋とられた。あとで水心子は笑って、朝尊にいった。
「実は、あの刀は折れないはずだが、お前があまり慢心していたので、自慢の鼻を折るためにやったことだ」
では、折れない刀をどうして折ったか、まず前の晩、朝尊の刀の切先を寒中の水に入れておいて、一晩中凍らせておいた。翌朝それを引き上げて、直ちに大きな台のうえに載せた。切先とナカゴがともに3~4寸(約9.1~12.1cm)台の外にはみ出すようにして置いて、ナカゴのほうを金槌で、こつこつと叩いた。すると、その反動で切先がぽっきり折れた。
「こうすれば、どんな刀でも折れるよ」
水心子は笑って、こう白状した、という(『刀剣研究』12~1)。自信家の朝尊にとっては、大ショックだったに違いないが、自分が井のなかの蛙だったことに気付いたのは、彼にとっては大きな収穫だったはずである。
「上には上がある。わしももっと天下に眼を向けねば・・・」
と、大いに発憤して、その後、各地の名工をたずね、鍛錬の秘奧を探った。そして天保(1830)年間、江戸は湯島天神のかたわらに、フイゴをすえ、大いに土音を轟かした(「土佐違聞録」)。そのとき近くに住む松井新八郎乗綱という旗本を門人にしたので、評判はいっそう高くなった。
その後、京都に居を移すと、まず伊賀守金道の世話で、権守を受領した。天保11年(1840)ごろの作に、よくこれを冠している。さらに金道家に同居して、その代作をするようになった(「服部押形」)。それは9代:金道が金工としての活躍に情熱を傾け、鍛刀のほうを顧みなくなったからである。
さらに朝尊の名を高らしめたのは、当時歌人として高名だった千種有功のお相手として、鍛錬に協力したり東寺の寺官:駒井安芸慶任を弟子にもったりしたことだった。そのほか、嘉永3年(1850)までに、十数名の弟子を養成している。朝尊はまた教育家でもあったことになる。
朝尊が郷里に帰省したとき、4キロぐらいしか離れていない佐川町から、古沢八左衛門義正という武士が訪ねてきた。この人は南洋と号し、土佐藩の家老:堀尾家の世臣で、実父を井原源三郎というが、望まれて無外流の名人:古沢与一左衛門の養子になった。他家から望まれただけあって、文武に長じ、子弟に教授していた。特に剣術で師範をつとめていた関係で、刀剣に関心が深かった。
「タトヒ撃剣ヲ能スト雖モ、又刀剣ニクハシカラザレバ、所謂、車ノ一輪ヲカクガ如シ」
と考えて、刀の折れ曲がり試験を数多くやってみた。ところが、新刀や末作の大出来物、つまり刃文の大模様なものは、2,3回打ち合ってみると、折れるものの多いのに驚いた。そこにたまたま朝尊が帰郷していると聞いたので、山路もいとわず早速やってきたわけである。そして朝尊に向かって、
「新刀ノ折レ易キ、恰モ朽タル木ヲ折ルガ如シ。何ゾ生命ヲ頼ムニ足ランヤ」
と、大いに憤慨していた。それを聞いて、かつて水心子正秀に自作刀を折られた経緯を、ほろにがく思い出しながら、復古刀のことを説いた。
「昌平久シクシテ人、華美ヲ好ミ、実用ヲ失フニイタル。今ニテモ真ニ武用の鍛ヲ知ルモノハ、古伝ニシクハナシ」
古刀流の鍛法について、いろいろ説明したところ、八左衛門は大いに共鳴して、さっそく朝尊に入門した(『新刀銘集録』)。八左衛門は維新後、東京に移住したが、明治9年(1876)7月7日病没した。行年68歳。生前、勤王の志が篤かったので、正五位を追贈された(『高知県人名事典』)。
つぎの刀も朝尊が帰郷したとき、頼まれて打ったものであろうが、朝尊の刀銘中では最長のものである。
土佐国高岡郡春木城主従五位武蔵守藤原朝臣家重十一代後胤谷脇勘解由藤原重之君応需
同国同郡黒岩郷二つ野村産森岡南海太郎朝尊於鳳城堀川一条作之
嘉永六年癸丑十二月中浣
ここに「鳳城」とあるのは御所のことだから、当時は京都を意味する。
朝尊は堀川一条から、嘉永7年(1854)、西陣に移った。西陣は御所の北方地区で、いわゆる西陣織の本場として、当時も大いに栄えていた所である。ここでの作に、8歳の嫡子:朝良を相槌にして作った短刀がある(『新刀銘集録』凸版)。
山城国西陣住朝尊
嘉永七年十二月日 子朝良八歳相造
西陣とは逆に南方、紅灯の巷として知られた島原の南に住んでいたこともある。
平安旧鴻臚館住朝尊
鴻臚館というのは外国使節の迎賓館であった。平安京造営のはじめ、東西二つの鴻臚館が建てられた。その場所は現在でいえば、下京区丹波口駅の南方、つまり山陰本線をはさんで、東鴻臚館は島原の南:正会町付近、西鴻臚館は堂ノ口町から北ノ口町にかけた一帯にあった。しかし、朝尊のいた旧鴻臚館とは東寺、つまり教王護国寺のことであろう。延暦15年(796)、東西の鴻臚館を廃して、東西の二寺にしたという。すると、東寺の全身は東鴻臚館ということになる。東寺の寺官:駒井慶任が朝尊の門人だったことは、既述のとおりである。その縁故によって、朝尊はしばらく東寺に駐槌していたものであろう。
なお、大坂においての作もある(『新刀押象集』)。
あし乃かり屋に造
ちやうそん
「あし乃かり屋」は、大坂または摂津の総称としてもいいが、次の歌を連想すれば、現在の芦屋市(兵庫県)とも解せられる。
葦のやのこやのわたりに日は暮れぬ
いづち行らむ駒にまかせて 能因法師
晩年には京洛の都塵をさけて、洛北岩倉の幡枝(左京区幡枝町)に居を移した。
山城国幡枝寓朝尊
文久元年二月日
鞍馬詣りのついでに、木野駅で電車をおりると、そこがバスの終点になっている。ここから乗車して南下すると、2つ目の停留所が幡枝である。幡枝の北端に近い山のうえに、昔は専修寺という浄土宗西山派の寺があった。明治初年、廃仏毀釈の嵐で跡形もなく消え去った。ただし戦後は再建されているが、それを「上の寺」とも呼んでいた。それより下のほう、つまり幡枝町福枝20番地に、「下の寺」と俗称された尼寺があった。
朝尊はまずこの尼寺に鍛冶場をこしらえた。槌の音が木魚の声とコーラスを奏でていたが、間もなく幡枝町の南庄44番地、つまり現在久世氏の屋敷になっている所に、居宅を新築した。南側に瓦びさしをつけた草ぶきの家だった。鍛冶場は母屋の南、唯今水田になっている所に建てられていた。「山城国幡枝寓」と切った短刀は、尼寺に寓居していた頃の作、つぎの刀銘のものは、44番地にわが家を新築してからの作、と見てよろしかろう。
城州幡枝 南海太郎朝尊(花押)
元治元年五月吉日
朝尊は幡枝産の土で刀を焼くかたわら、剣術も教えていた。戦前、95歳の老女の話では、剣術を村の子弟に教えていたという。朝尊みずからも『刀剣五行論』のなかに、
「予も亦幼年之時より兵法剣術を志、初ハ万水流を学、後転じて諸流に渉り、一旦豁然として心を歉(欹か)て、一流に究む。名けて気心流と号する也」
と述べている。万水流の名は『武芸流派事典』にも見えていないから、土佐にあった小派であろう。とにかく、みずから気心流の開祖をもって任じているほどだから、相当の剣客だったことに間違いない。朝尊は左利きだったから、彼の剣術も左利きを活用したもので、初めて立ち会った人は面食らったことであろう。
朝尊が左利きだった証拠は、刀銘を見ればわかる。銘字の横線をみると、右のほうが太く、左にゆくに従って細くなったものがある。これはタガネを右から入れて、左に抜いたことを示すもので、これはタガネを右手に、槌を左手に持っていた、つまり左利きだったことを物語るものである。ナカゴ鑢が右上がりになっているのも、左利きを示すものである。それを朝尊みずから立証したものとして、初期銘に「左手朝尊」と切ったものがある。それほど、彼の左利きは有名だったのであろう。
左手朝尊
文政十三年十月日
左利き剣法で腕に覚えのある朝尊が、胡麻の蝿を防いでやった、という話がある。ある日、旅行中のこと、彼の烱目は胡麻の蝿がある旅人をつけているのを、素早く看取した。そこで持ち前の男気を出して、胡麻の蝿につけ入る隙を与えなかった。とうとう一指も触れさせなかったので、旅人から感謝されたのは勿論であるが、胡麻の蝿も感服して、
「旦那にかかっちゃかないませんや」
と、頭をかきながら、酒をおごってくれたという。気心流の開祖も、この振舞い酒にはほろ苦さを感じたことであろう。
もっとも胡麻の蝿がこわがったのは、朝尊の左利き剣法ではなくて、彼のご面相だったかも知れない。南海太郎朝弘ははじめ朝尊に手解きをうけたのち、左行秀・月山貞一・尾崎正隆などにも鍛法を問うている。土州香美郡片地むら中筋(土佐山田町)の住人で、昭和8年、95歳で没している。(浜田晃僖氏調べ)。この朝弘の談によれば、朝尊は痘痕の大男だったという。戦前、幡枝に84歳の老翁がいた。その人も、
「朝尊は頭の禿げた、痘痕面どした」
と、述懐していたから、ご面相のほうは、お世辞にも上等とはいいかねた。さらに子孫の人の話によれば、額の出っぱった、土佐でいうデブチンだったという。どうも風采では鬼をもひじくマスラオだったようである。胡麻の蝿がより付けなかったのも無理はない。
頑強そのものの朝尊は、故郷忘じ難し、というが、老年になっても、たびたび土佐に帰っていた。高知城下では、尾戸といって茶碗をやく村に行って、そこの小林三郎兵衛宅で刀を打ったという(秋山久作談)。
いくら頑強でも、死神には勝てない。朝尊も幡枝でそれに捕えられ、慶応元年(1865)4月7日、61歳であの世に連れ去られた。旧土佐藩士で、明治のころ鑑定家として知られた今村長賀が、慶応2年(1866)8月7日没、享年61、と発表したため、今日の刀剣書はそれを採用しているが、長賀の記憶違いである。専修寺の『霊名簿』は操ってみると、「慶応元丑年」の部に、次のように記載されている。
四月七日
尊誉鍛光流海居士 森岡孝之助 六十一歳
朝尊の遺骸は、遺族や門人の手によって、専修寺墓地の入り口近くの一角に、ねんごろに葬られた。しかし嫡子:朝良は病身で早世、次男は他家へ養子に行ったため、無縁同様になってしまった。それで墓碑はもちろん、目印になるものすら何一つ残っていない。
しかし、土佐の森岡家ではそれから27年後、つまり明治24年(1891)になって、大の城にある同家の墓地に、つぎの碑を立てた。
明治廿四年八月日
南海太郎朝尊
森岳又次建之
これは幡枝の墓を改装したもの、ともいう(今村長賀談)。それならば他の墓と同様に、「南海太郎朝尊墓」と、墓の字がつくはずだし、また没年が記入されるはずである。それなのに、建碑の年月だけ誌してあるのは、供養塔として建てたことを暗示するものである。
朝尊の妻は専修寺の霊名簿によれば、慶応2年(1866)11月27日卒、法名諦誉聴善恵海大姉となっている。
悲運な子供たち
朝尊に虎丸、のち虎太郎とよばれた、朝良という嫡子のいたことは、朝尊が自著『新刀銘集録』に紹介しているので、よく知られている。朝良は早熟な子で、8歳のとき、父との合作刀を残していることは、既述のとおりである。さらに安政4年(1857)には、わずか11歳で、「虎丸」と切った短刀を世に出している。
早熟なだけに、世を去ることも早かった。戦前、84歳翁が語っている。
「朝尊は男の子が二人いましてナ、長男の久太郎は35ぐらいで死によりました。次男の幸太郎は、下賀茂のコーマン所という塾の小使をしている家に、養子に行きよりました」
久太郎というのが朝良の成人後の通称である。35歳といえば明治14年(1881)のこととなる。廃刀令後まで生きていたことになるが、絶えて遺作に接しない。84歳翁は、
「気の毒なことに、朝尊の家は肺病患みの血統でして-」
と、老の眼をしばたいていた。すると、朝良も胸の病で刀はほとんど打てなかったのであろう。なお、朝尊には馬之助という子供がいて、京都の五条通りで、剃刀を作っていた、という伝説が土佐にある(浜田晃僖氏談)。しかし、朝良の家のことをよく知っていた84歳翁は、馬之助の存在を口にしなかった。すると、馬之助とは朝良の子、つまり朝尊の孫ではなかろうか。
朝尊にはオタミという娘がいた。
「それも可哀そうに、20ぐらいで亡くなりましたわ。やはり胸の病で・・・」
そういう悲惨な一家だったので、新々刀史上に大きな足跡をのこした朝尊の墓も、遺族の手によって建てることは不可能だったのであろう。
朝尊の著書
朝尊には「刀剣五行論」「新刀銘集録」「宝剣奇談」など、三部の著書がある。
①「刀剣五行論」
本書の刊本には、嘉永3年(1850)3月の自序があるが、実際に発刊されたのは2年後の嘉永5年(1852)6月だった。何しろ自費出版であるから、相当の出費が必要だったはずである。幸い京都の越後屋治兵衛・山城屋佐兵衛という二軒の本屋が、発売元になってくれはしたが、あまり売れなかったようである。と言うのは、今日ほとんど見受けないからである。
本書は上・下の二巻に分かれているが、上が14丁、下が13丁、計27丁に過ぎないので、1冊として製本、発売されている。
さて、内容であるが、まず巻頭に掲げられた自序を見ると、漢文で綴じられている。朝尊の教養をうかがうにに足る資料であるから、つぎはそれの仮名交じり文になおしたものとなる。
夫レ刀剣ハ国ヲ治メ、家ノ守護ト為(ナ)ス。上ハ朝(庭)廷ヨリ下ハ衆民ニ至ル。頂(頃)刻モ身ヨリ放タズ、其ノ用ヲ為(ナ)ス。兵器ノ第一也。天目一箇神ヨリ今日ニ至リ、伝エテ造ル者有リ。鍛錬ノ法ハ斯利倶利伽梅儺波曳結界、怨神ヲ退ケ、心神天地に満チ、五行ノ神徳ヲ戴キ、金火水土ノ利ヲ
悟リ、身ニ炭灰ヲ被リ、面色、汗ヲ浸シ鬢髪鬅々、浄服、散火ニ破レ、身躰、異仙ノ如シ。朝暮、飯喰ヲ忘レ工夫連行スルコト猶久シ。其ノ術、或イハ微妙ヲ得ル者ハ、威名広く天地赫ク如(モ)シ妙利ヲ得ザル者ハ、人竟(ツイ)ニ知ル無シ。数百年後ニ至リ、或イハ国知レズ、或イハ銘鑑ニ洩ル。生前何ノ為、身ヲ修メ心ヲ尽シ業ヲ学ベル哉。余之レガ為、先ズ五行ノ利ヲ明ラカナラシメント欲シ、此ノ冊二ヲ綴り、乾坤ニ分カチ、木ニ鏝(キザ)ミテ後世ニ伝ウ
嘉永三年庚戌三月 南海太郎朝尊(印)
朝尊が漢文を書けるような教養を、どこで身につけたか、明かではないが、『新刀銘集録』に、梁川星巌・貫名海屋・池内陶所など、当時の錚々たる学者が序文を寄せているところを見ると、これらと普段から交遊があったに違いない。すると、朝尊は鍛法のみならず、学問のほうにも相当情熱を傾けて、勉強したはずである。
さて、本書は題名の示すとおり、五行説の立ち場から刀剣を論じたものである。五行説は中国における古代からの宇宙生成論であって、万物は木・火・土・金・水など、五つの要素から成っている。と説く。この説はわが国でも広く信じられていたので、朝尊もこれに基づいて、刀剣を論述したわけである。
まず、第一の木性の部では、刀を鍛えるのに不可欠の木炭について、その製法を具体的に詳述している。第二の「火性」については、火を起こす方法をあげている。第三の「土性」においては、刀工の秘伝である焼刃土について述べている。第四の「金性」については、鉄の種類や産地、さらに製鉄法まで細説している。恐らく鉄山に行って、親しく見聞した結果を書いているのであろう。第五の「水性」については、刀工の秘密にしている焼入れ水について、いろいろ述べているが、
「此国京都ハ北極地三拾六度ト云説も有れども、正則ル所ハ、三十五度之余而、六度ニハ足ラズ」
と、科学的な知識を披露しているのは、ちょっと意外である。上巻の終わりは「五色之変」で結んでいる。そこに、なまず肌・晒し鍛え・おろし鉄など、鑑定にも関連ある事項の説明がなされている。
下巻はまず「鍛之法」から始まっている。これには種々の鍛錬法が紹介されている。そのなかに、
「俗説ニ古作ハ一鍛を加えず云者有」
とあるが、これは水心子正秀のことである。朝尊はこの説を否定しているから、水心子入門説は真実でないようである。第二の「焼刃渡之事」には、普通の焼刃土のほか、薬焼刃のことも解説している。
第三に「造刀心気之法」を掲げている。これは刀を打つときの心構えを述べたもので、不動明王や不動智の説明をしているところを見ると、朝尊は精神家でもあったようである。第四にあげた「武用之事」では、相州行光や備前長光の刀を打ち折って、研究したこと、郷義弘・行光・左・康光・盛光などを焼き直して、調べたことなどを述べている。その結果、棟金や心金をよく鍛えて、折れない刀を造るようになったという。最後に「荒硎之事」の項を設け、研ぎの解説をしている。
以上のとおり、刀剣の全般にわたり、刀鍛冶の立ち場から論述したもので、よく纏まっている。知能指数の高い男だった証拠である。
②『新刀銘集録』
本書の自序は、嘉永3年(1850)8月の日付になっている。すると『刀剣五行論』よりわずか5か月後に成ったことになる。しかし発売は『刀剣五行論』より5年も遅れている。五巻本であるため、京都の本屋は手を出しかねたらしい。大坂の前川文栄堂が版元になっている。
本書は戦前の旧版『日本刀講座』に収録されているが、当時の大家のよせた序文は、自筆のまま版にしてあるため、読めなかったのであろう、省略してる。しかし梁川星巌・貫名海屋・池内陶所など、当時の大家のよせた序文である。省略するのは不合理だから、つぎに原文のまま掲げておく。
武備機械雖多、其人々身上朝夕所随而、生命所寄、無近且重於刀剣。近且重則其不可不択也審矣。乃其利鈍精粗品格高低、系譜流派以及真贋吉凶等之区別、非平日所講究、則難乎可
遽弁明。其講究弁明必待銘鑑。刀剣之有銘鑑、猶書画家之有譜論不可闕矣。是故廻明記之後、『古今銘鑑』『古刀銘集録』『新刀弁疑』『刀剣或問』等之作、嗣出而刀剣亦日新。安永巳後、未有集。此者夫代遠者難究而疑生時、近者易求而証明。然其間、若無勒之者歳月則荏苒易遷。其易求者将主難求。今刀匠朝尊之所以有此挙也。朝尊近日頗有名誉之者。遊歴諸国集此書。又別著五行論、審其製作要訣。可謂匠中所罕見者矣。刻成来乞題言。余因問諸国名匠之後、則子孫縄々不絶者無幾。亦可慨也。朝尊称南海太郎、土佐人、寓于京師
嘉永庚戌之秋八月 鴨東 菘翁題(印)
菘翁とは貫名海屋のことである。儒・書・画の三道に達した有名人で、須静塾を開いて教授していたこともあったが、当時は下鴨の加茂御祖神社に奉仕していた。それで「鴨東」、つまり鴨川の東と書いたのである。当時既に73翁で、京都文人の長老であった。その人から直筆の序文をもらったのだから、朝尊も感激したに違いない。
題辞
手提三尺寒支那、功業雖昌社屢遷、何似天縁藁雲剣、神光不絶万斯年、也知糞土一重々、出気豊城伏二竜、若夫張華真識気、人間随処有神証
丁巳新正 星巌 六十九翁 孟緯
梁川星巌は「日本の李白」といわれたほどの大詩人であった。それで序文のかわりに自作の詩を寄せている。時に歳69、つまり死の前年にあたる。
余素有刀剣癖、頗喜賞鑑而自古至今、刀匠之多無慮数百千工、不能徧観而尽識故、或不得不徴之於刀剣之書。願其為書亦不下数十種、而安永以還則闕如。余常以為憾。南海太郎朝尊当今良匠也。以所著新刀銘集録見分。余受而閲之、安永以還刀匠之譜系宗伝及刀茎款識、瞭如指掌。余嘉其有稗於賞鑑家也。及刻成為引其端。
安政丁巳之花朝 陶所 池内時識(印)
陶所とは池内大学のことである。当時、星巌について学名を謳われ、青蓮院宮や三条内大臣の知遇をうけていた。安政大獄ではとうてい免れない、と観念して、自首したので、中追放という軽い処分ですんだが、勤王の志士たちからは、裏切り者として睨まれていた。それで文久3年(1863)、土佐の岡田以蔵から暗殺された。しかし、この序文を書いたころは、勤王派として高く評価されていた。随って朝尊も序文をねだったわけであろう。そのことは、朝尊にも尊王の志のあったことを物語るものである。
つぎに朝尊がみずから書いた自序であるが、それに本書編術の趣旨をこう述べている。
「安政中に書を著せし『弁疑』よりこのかた、今現存の人々にいたるまで、一流一派の続きを鮮にせむと、幼なきより州郡を廻り、手帖にとどむるところの銘をよせて、『回明記』、一名『新刀銘集録』と題す」
すると、本書は『回明記』というのが、正式の題名ということになるが、『古今銘尽』の奥書に、すでに「参河入道以前者、正宗国々廻明記也」、とあるし、なお『新刀銘集録』のほうが内容にふさわしいので、出版元の希望によったに違いないが、副題のほうが正式の書名になってしまっている。
いよいよ内容であるが、巻之一から五までは刀工系譜で、巻之一は五畿内、巻之二は東海道、巻之三は東山道・北陸道、巻之四は山陰道・山陽道・土佐以外の南海道、巻之五は土佐・西海道という国分けになっている。
巻之六以下は押形とその解説である。巻之六は五畿内・山陰道・山陽道・巻之七は南海道・西海道、巻之八は東海道、巻之九は東山道・北陸道・諸州集・朝尊自筆の跋文、という内容になっている。
内容からいえば『新刀銘集録』でなくて、『新々刀銘集録』でなければならぬが、当時はまだ「新々刀」という言葉がなかったので、止むを得ない。しかし、新々刀に関する最初の系譜ならびに押形集である。独力でよくこれまでやれた、と敬服するほかない。
③『宝剣奇談』
本書の近刊予告が『新刀銘集録』の最後に出ている。
「本朝に往古より語伝へたる宝剣の故事来歴、奇瑞妙語を集め、杜撰附会の俗説を正して、悉く古書に拠て編著なしなれば、其実伝を明に知る本なり」
しかし「近刻」という但書がついている。今日これを実現した先輩がいないところを見ると、大坂の前川文栄堂が出版するはずであったが、なんらかの理由で陽の目を見なかったものであろう。予告にあるとおり、「古書に拠て編著」したとすれば、朝尊は相当の学者だったことになる。それは『新刀銘集録』に、当時の錚々たる学者が序文を寄せている事実からも、ほぼ納得できるであろう。しかし、その実力のほどを、『宝刀奇談』の出版中止によって、窺い知ることができなくなったのは、まことに残念である。
(参考文献:日本刀大百科事典より転載・引用・抜粋)
#南海太郎朝尊