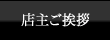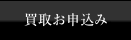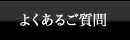長巻買取
長巻きとは、長い刀身に、それより少し短い柄をつけて、薙刀のように手に携行するものいう。長柄刀より長いもの、長柄巻きの略で、または長巻きの太刀・長巻きの野太刀の略とも、あるいは中巻きの濁ったものともいう。
長巻きが出現した室町期には、長さ五~六尺(約151.5~181.8cm)、形は木刀のように刃はなかった。半分より下を紐で密に巻き、そこを握って人馬を薙ぎ倒すのに用いた。柄も鞘もないので、携行するときは二カ所に紐をつけ、背中に斜めに負うたものだった。
それでは体裁が悪いので、のちには薙刀にならって、刃をつけ、柄をつけるようになった。刃をつけ、柄をつけるようになった。織田信長は長巻きの有利なのに眼をつけ、刀身を三尺(約90.9cm)余、柄を四尺(約121.2cm)余にして、長巻きと名づけ、鞘なしで徒歩のもの百人に持たせた。それを長巻きの組手といい、信長の馬前を行進させた。
上杉謙信は長巻きを身脇衆に持たせたり、雑兵に持たせて、敵の騎馬武者の駆る馬の脚をそれで払わせたりした。それで同藩では長巻きを、馬の脚払い、と呼んでいた。中国でいう斬馬刀は、うまをも切るほどの鋭利な刀といいみである。長巻きを豊臣秀吉が木下藤吉郎時代に考案したもの、とする説は誤り。
長巻きの柄は二尺(約60.6cm)のもので、それより長さが短いものは長柄刀と呼んで区別した。刀身の長さが二尺三寸(約69.7cm)ならば、柄は二尺(約60.6cm)とするのが標準だった。刀身の長さは三尺七寸(約121.2cm)が限度とされていた。柄は樫の木でつくり、柄の上半分には細かい鮫皮をきせ、その上を紐で片手巻きにする。下端には石突きをはめる。刀身には鎺をつけて、さらに鐔や切羽をそうちゃくする。
中巻きとは、中巻きの太刀の略で、長巻きに同意となる。熱田神宮の祭礼に用いる長巻きも、ナカマキと発音する。天正18年(1590)、小田原城攻めのさい、徳川家康は豊臣秀吉より贈られた中巻きの野太刀百振りを、武州八王子の千人組に持たせた。越前福井藩には黒脛巾者とよばれる一団があった。藩主の馬の前後に従い、中巻きを持っていた。その中巻きは三尺(約90.9cm)ほどの刀身に、三尺ほどの柄をつけたもので、柄は笛巻きにし、鞘はないものだった。「日葡辞書」に、中巻きを、鞘に入れないで携行した長めの短刀、と説明しているのは誤解。
長柄刀は、柄を特に長くした刀。これに腕貫きをつけた刀が、関東では北条氏直の時代まで流行した。その起原は、鹿島明神が老翁の姿で現れ、林崎勘助藤吉(甚助重信)に、長柄刀の利を教えたのが、始まりという。林崎はそれを田宮平兵衛成政(重正)に伝えたので、田宮は諸国修行して、この術を弘めたという。林崎は慶長(1596)ごろの人で、居合い術の始祖とされている。文禄(1592)ごろの土佐光純や土佐光益の風俗画に、長柄を描いたものがあって、腕貫きを二カ所に付けている。しかし、世が泰平になると野暮だとして、慶長(1590)ごろになると、姿を消したようである。
田宮平兵衛は、「長柄に八寸の徳、見越しに三重の利あり」、と説いた。山浦清麿のパトロン:窪田清音は、田宮流から一派をたてた人であるが、居合い術の見地から、普通より二寸(約6.06cm)ほど長柄にすれば、刀身が二寸長くなる。二寸長くなったことで、相手との間合に二寸の利、相手に届きやすい利、相手からは届きにくい利、以上の四利が二寸のために生じるので、「八寸の徳」という。されに長柄にすれば、上太刀に構え、相手を眼下に見る利、相手からは間合が遠いため、こちらに近づきにくい利、逆にこちらからは、相手に近づきやすい利、以上の三利を「見越し三重の利」という、と説明している。
窪田清音の長太刀術では、刀身が二尺五寸(75.8cm)の太刀ならば、一尺二~五寸(約36.4~45.5cm)の柄をつけた。柄は朴の木を用いた。長太刀を佩いて馬に乗るときは、馬の左より、腕貫きを口にくわえて乗ることになっていた。なお、柄を二尺(約60.6cm)以上の長さにしたものは、長太刀はといわずに、長巻きと呼んでいた。