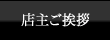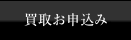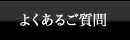槍買取
槍とは、先端を鋭利にした刺殺用の武器で、中国で古くは、木の先端を削り突き刺すのに用いていたので、木偏に音符として倉(そう)の字を加えた。わが国でいう木槍・竹槍の類である。中国で槍を最初に使ったのは、黄帝が蚩尤と戦った時、槍の先端に鉄の穂をつけるようにし諸葛孔明、ということになっている。矛の一種だからとも書く。
槍に鉄の穂先をつけるようになったので、槍の字を代わりに、金偏のついた鎗という字を遣うようになった。しかし、鎗という字は鐘の音の形容、または六斗四升いりの釜のことで、武器としての意味はないが、唐のころすでに槍の意味に遣われている。形もいろいろ考案され、単鈎鎗・双鈎鎗・素木鎗・鵶頂鎗・錐鎗・梭鎗・槌鎗・拒馬鎗・鏟・鎲など、種類が多かった。なお、現今は鉄砲のことを鎗という。機関鎗といえば機関銃のことである。
わが国では古く槍の字をホコと訓んでいた。長槍・茂(いかし)槍・杖槍・木鎗などは、その例である。長鋒と書いて、ヤリと訓ませた例もある。古くは遣刀と書いたものもある。しかし、「太平記」に鑓という字が考案し、使用しはじめて以来、それが広く用いられるようになった。槍は古代の鉾より柄が長く、遠くまで突きヤルことができるので、初めヤリ鉾といったのを略してヤリと呼ぶようになった、と推測されている。
「後三年合戦絵巻」に、笹穂の槍と見える図がある。これを書いた飛騨守惟久は、鎌倉期から南北朝期にかけての人であるが、「後三年合戦絵巻」は、すでに平安末期の承安四年(1174)に描かれたものがあり、さらに将軍実朝が承元四年(1210)、「奥州十二年合戦絵巻」を見た、という史実がある。すると、飛騨守惟久が槍の図を描いているのは、これら古い両絵巻にも、槍の図が描かれていたからであろう。なお、鎌倉末期の元亨三年(1323)の奥書のある「拾遺古徳伝」にも、槍の絵が描かれている。
飛騨守惟久筆の絵巻物の詞書には、「鉾」の字を書いているが、これは僧玄恵が、南北朝になってから、正平二年(1347)に綴ったものである。後三年の役当時に遡って、ホコという古い名で呼んだものである。それよりずっと古い寿永二年(1183)二月、敗軍の将:平忠度・敦盛らの首を、京都の四条河原にさらした時、首は「長鎗刀」に突き刺してあった。源頼朝が島津忠久に「長槍」を与えた、という説もある。
大坂の非人頭:弾左衛門家の伝説によれば、源頼朝が弾左衛門の先祖に、朱柄の大身槍を三本預けた。一本は磔刑のとき、罪人を突くのに用いた。他の二本は、大坂の渡辺と小浜にいる手下の者に預けてあった。享保(1716)のころもそうだった、というが、それは弾左衛門の創作であろう。
以上のように、鎌倉期の資料に、槍という字はすでに多く使用されているが、これをホコとよむか、ヤリとよむかは分明でない。はっきりヤリとよんだ資料の登場を見るには、南北朝期初頭の元弘四年(1334)まで、待たねばならなかった。その前年(1333)、現在の青森県南津軽郡平賀町にあった大光寺城を、南朝方の北畠軍が攻めたとき、城にこもる北朝方の矢木弥二郎というものが、「矢利」をもって胸を突かれ、半死半生の重傷を負った。そのことを元弘四年(1334)正月十日付で、報告した文書が、今のところ槍の名の初見とされている。
槍の起原については、古来幾多の説があった。最も古いのは、楠正成が創ったという説で、つぎは楠一族の和田賢秀が、暦応(1338)年中に創った、という説がある。さらに室町期に降って、嘉吉(1441)の乱のとき、利剣を竹の先につけて、武器にしたのが始まり、ともいうが、もう少し降って、応仁(1467)・文明(1469)のころできた、とする説もある。以上の諸説は、いずれも臆測や付会で、事実に合わない。
槍の実物の方からみると、まず奥州の伊達家に、天国の作と称する七寸三分(約22.1cm)の槍があって、伊達政宗は上洛のとき、これを持っていった。三条宗近は槍、特に石戦鑓を作った。それには百本形・千本形の別があった。宗近の子:吉家も槍を多く造った。奥州二本松城主:丹羽長重所蔵の「篠切り」の槍は古備前友成の作だったという。以上の諸例は真実だったとしても、ヤリでなく、ホコと呼ぶべきであろう。
しかし、古剣書の説には否定し難いものがある。大和の当麻次有の槍は、越智鑓といって有名だったが、槍造りは曽祖父の国行の代から行っていた。無銘であったため、単に当麻鑓の名で古剣書に出ている。その国行には宝治二年(1248)、つまり鎌倉前期の作がある。京都では前掲の三条吉家はおくとして、革堂槍が有名だった。それを作った粟田口有元や有光は、建長(1249)ごろ、というから、当麻国行と同時代である。さらに降って建治(1275)ごろ、つまり鎌倉中期の当麻才光と、千手院長光が名人とされていた。以上のように古剣書では、古く鎌倉期から槍のあったことを認めている。
槍の部分的名称は右図の通りで、先端の金属の部分を、穂または身、柄のなかに入る部分を中心、穂の先端を穂先、穂の中央に縦に走っている稜線を鎬、穂から中心への移行部分、つまり幅が狭くなり、刃もついていない部分を螻蛄(けら)首・潮(塩)首、刃のある部分と螻蛄首との境目を区(関)という。柄の挿し込む部分を、中心または込みといい、それに目釘孔と鑢目がある。
穂をさし込む長い棒を柄といい、柄の上端には割れるのを防ぐため、口金をはめ、さらにそれに続いて、逆輪という金具をつける。それより間隔をおいて、胴金という輪をはめ、それに槍印をつける環(幟付け鐶)をつけたものもある。なお、目釘の脱落防止に、目釘孔のうえに動くようにした、目釘留めの輪をはめることもある。胴金よりさらに間隔をおいて、緒を巻きつける。これを血留め・手溜まり・鏑巻きなどとよぶ。この血留めから口金までを、太刀打ち・太刀走り・太刀受けなどという。柄の下端にはめた金具を石突き(鐏)、その上にはめた金具を、水返しという。
以上のほか特殊のものとして、鍵槍では胴金のところに、複数の型の横手をつける。管槍では胴金が上下に、自由に動くような管になる。袋槍では中心が管状になり、逆にそのなかに柄をさし込むようになっている。
穂には種類が非常に多い。まずその横断面からみても、正三角形・平三角形・両鎬(菱)形・鎬造りの刀身形・梯形など、種類が多い。全体の姿、つまり造り込みは大別して、直槍と鎌槍の二種があり、それぞれにまた種類が多い。
穂の長短によって、長槍・長身の槍・大身の槍・大実の槍・中身の槍・小槍・三寸穂などの別がある。
槍の使用方法によって、儀仗と兵仗に大別する。儀仗は多く鉾の形式になる。兵仗としては、手槍・持ち槍・替え槍・番槍・立て槍・物見槍・対の槍・御諚槍などの別がある。
槍の作者として、山城の革堂槍はこんにち見受けないが、信国はある。もっとも多く現存しているのは、平安城長吉と三条吉則である。大和の越智槍も遺作を見ないが、室町末期、金房派の槍は多く残っている。特に十文字槍は有名である。摂津では新刀の津田助広・井上真改・河内守国助などに見る。伊勢では村正、尾張では政常に名作がある。三河の文殊正真の「蜻蛉切り」は本多忠勝所持として有名である。駿河では島田義助の一門、相模では末相州の助広・広正・康春などにある。武蔵では下原派に槍が多い。新刀には少なく、新々刀になると、また少し出現する。
美濃では、加藤清正の娘の兼重作、大身槍があるほか、兼定・兼元・兼房・兼貞などに遺作を見る。近江では古く天九朗俊長が槍の名人と謳われたほか、下坂派の遺作もかなりある。奥州では、槍はあまり造らなかった。北陸にまわると、越中の宇多物、加賀の友重・兼若などに見る。山陰にもあない。備前では室町期の経家・法光・勝光・宗光・忠光・祐定など、それぞれ名作を遺している。備中では水田国重・安芸では輝広が造っている。
南海道では、紀州熊野の実次が名人といわれている。南紀重国の作もよく見受ける。西海道では、豊前の筑紫信国が、袋槍という特殊な形をつくったので有名である。その末流である筑前信国も槍を得意としていた。肥後の延寿派は、片刃の菊池槍を創作し、菊池氏の勤皇を支えたことで知られている。末古刀の同田貫派は、加藤清正の好みに応じ、大身の槍を多く作っている。