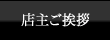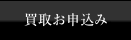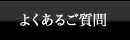巴形薙刀
巴形薙刀(ともえがたなぎなた)
- 薙刀
巴形薙刀は薙刀の形で、切先のほうが強く反り、かつ幅広になったもの。ただし、これは江戸期になってからの命名である。巴御前所持の名に因んだものではないが、江戸期になってから、婦人用に作られた薙刀の形となる。因みに京都上京区の興聖寺に、巴御前所持として「吉次」と在銘の薙刀や、木曽義仲所用として、「波平家次」在銘の太刀が伝来していた。
薙刀は敵を薙ぎ切りにするための長柄の武器で、そのため先の身幅を広くし、かつ反りを強くし、長い柄をつける。古くは那岐刀と書く。長刀・薙太刀・投刀・長打ち物・薙釤とも書く。釤は大鎌という意とき、実戦に使用させた、という説がある。異国の武器とは、中国の眉尖刀であろう。東夷征伐は宝亀11年(780)に行われた、伊治君呰麻呂の叛乱をいうが、この時代はまたホコの時代で、薙刀の出現は虚説である。光仁天皇は自ら刀をつくり、銘を「白壁」と切った、という古剣書の虚説から思いついた創作であろう。
平清盛が薙刀の利を強調したため、一門がみな用いるようになったので、天下に普及したともいう。清盛には厳島明神から小薙刀を授かったという伝説がある。これもその伝説からの創作であろう。薙刀が後三年の役のころから使用され、南都の僧兵も愛用していたし、彼らに薙刀を供給する刀工も、すでに平安期から奈良にいた。したがって平清盛説も信じがたい。
薙刀の最古の形式は長刀という字をあてているように、菖蒲造りの刀に長い柄をつけただけのもので、軍記物に「茅の葉の如なる大長刀」、「大長刀の茅の如なる」、とあるのがそれである。しかし、それでは先が軽過ぎ、切れが悪いので、鎌倉期になると、先の身幅を広くし、かつ反りも深くするようになった。当時描かれた絵巻物を見ると、そのようになっている。あるいは、さらに重みをつけるため、中国の偃月刀や筆刀のように、棟のほうに山形の突起をつけたものさえ出来た。無爪薙刀というのは、この突起のない薙刀のことであろう。薙刀では、先のほうの反った棟の部分を湾形、その反対側の刃のほうを、坂刃という。
時代がさらに下がると、「たひらにてしのぎさがりに菖蒲形」、とあるように、先のほうは冠落としての格好になった。つまり、先のほう三分の二が冠落とし、元のほう三分の一が本造りとなり、そこに腰樋と添え樋をかくようになった。この割合いを、水心子正秀は「三つ割り」と呼び、薙刀造りの基準にしている。なお、正秀は、大薙刀では元幅より先幅を2分5厘(約0.8cm)、中薙刀では2分(約0.6cm)、小薙刀では1分5厘(約0.4cm)、広くするのが定法、と述べている。もと三分の一のところにかく腰樋の上端は、普通∧型に尖らすので、この型の腰樋と添え樋を総称して、薙刀樋とよぶ。
薙刀の鍛法としては、三枚鍛え、つまり刃鉄・皮鉄・心鉄の三種を組み合わせる。焼きを入れる時は、物打ちは物に強く当たる所であるから、特に焼きを強く入れることが肝要という。
江戸期になると、形のうえに男薙刀と女薙刀の別を生じた。男薙刀は長くて、先もさほど幅広にならず、反りもさほど深くなくて、専ら実戦用だった。女薙刀はこれに反して、刃長が短く、先幅が広く、かつ反りも深く、非実践的な形になった。非力な女性の体格に応じて、刃長を短くして、扱いやすくしたものだが、それでは重みが不足するので、先幅を広くし、かつ切れをよくすため、反りを深くしたわけである。武家の婦女の武術として、薙刀術が専ら行われたので、嫁入り道具の一つにさえなった。
江戸期になると、男薙刀の形のものを静型、女薙刀の形のものを巴型、という名称を生じた。静は源義経の妾:静御前、巴は木曾義仲の妾:巴御前の所持、という意味である。なお、静型はシズカ型ではなく、シズ型つまり志津型で、濃州志津三郎兼氏作の薙刀だ、という異説もある。しかし、薙刀術に静流・巴流があるので、それに倣っての造語と見るべきであろう。
薙刀の中心は、槍と同様に柄のなかに長くさし込み、目釘を打つようになっているが、希れに袋薙刀といって、中心が筒状になり、その中に柄をさし込むようになったものがある。中心がなくて、刀身の元のほうに、鉈のように環を設け、その中に柄をさし込むようにしたものは、筑紫薙刀とよばれる。形状から鉈薙刀ともいう。そのほか、十文字槍や片鎌槍のように、薙刀に鎌をつけた十文字薙刀や片鎌薙刀とか、薙刀の先端を鯰尾形にした鯰尾薙刀などもある。
古い時代の薙刀はいずれも長寸で、軍記物を見ると、冷泉隆豊の2尺5寸(約75.8cm)は例外的に短く、それ以外は、坂四郎永覚の3尺(約90.9cm)、大内義弘の3尺1寸(約93.9cm)、大塔宮・阿闍梨祐慶・筒井明春らの3尺5寸(約106.2cm)、畑六郎左衛門の3尺6寸(約109.1cm)、塩屋伊勢守の4尺(約121.2cm)、滑良兵庫頭の5尺2寸(約157.6cm)、和田源秀の6尺(約181.8cm)余、長尾弾正や熊野人の6尺3寸(約190.9cm)、安積彦五郎の8尺(約242.4cm)余などと、超大型の記載がある。
当時は薙刀を大薙刀・小薙刀の二種に分けていたが、その区別はあいまいなものだった。豪鑒・豪仙らの4尺(約121.2cm)、澄憲や祐慶の3尺(約90.9cm)、大内義長の2尺8寸(約84.8cm)を大薙刀、大塔宮や和田五郎の3尺5寸(約106.2cm)、薬師寺十郎次郎の2尺5寸(約75.8cm)を小薙刀、と呼んでいるところを見ると、厳密な区別はなかったことになる。
鎌倉時代に描かれた絵巻物を見ると、「月の如くそりたる」とか、偃月刀とかいう名称にふさわしく、先のほうで、「へ」の字形に、2寸5分(約7.6cm)くらいも反っている。この薙刀の標準型に対して、反りの浅いものを、小反り刃とよんでいた。なお、「へ」の字型がさらに曲がり、鎌に近くなったものも、絵巻物に見られる。室町期の加州家次もこの形のものを造っている。これは薙刀に薙鎌の用を兼ねさせたものである。
薙刀の柄は槍の柄とちがい、普通楕円形で、樫の木をもって作る。白木のままのものを白柄といい、「平家物語」などの軍記物には、しばしば特に「白柄の長刀」と断ってあるから、普通は漆塗りだったと見える。上流の持ちものは、それに金や銀の蛭巻きなど施してあった。平清盛が厳島明神から授かった小長刀、源頼朝が義朝から相伝の小長刀は、いずれも柄が銀の蛭巻きになっていた。豊臣秀吉が自ら朝鮮へ出陣の時のため、用意させた薙刀は金熨斗付けの柄だった。薙刀には鐔がないのが普通であるが、古い絵巻物には、鐔のある薙刀の図もある。柄の下端に金具、つまり石突きをはめることは、槍と同じである。
柄の長さは持ち主の力倆によって異なる。薙刀の刃長6尺(約181.8cm)に、柄は1丈(約303.0cm)と柄のほうが長いもの、刃長6尺(約181.8cm)に柄も6尺、刃長5尺(約151.5cm)に柄も5尺と、同じ長さのもの、刃長4尺8寸(約145.4cm)に、柄は3尺5寸(約106.2cm)、と逆に柄の短いものもある。しかし、刃長2尺3寸(約69.7cm)の薙刀の柄は、持ち主の耳たぶの下端の高さ、というのが大体の長さであろう。
薙刀の作者として、軍記物には「備前長刀」の名がよく出てくる。「近江うったる長刀」、と個名をあげたものもある。そのほか「鎌倉鍛冶の鍛うたる大長刀」、という記述もある。木曽義仲相伝の三重宝で一として、大和の「竜王作の長刀」があった。なお、静型の薙刀の「静」を、志津三郎兼氏の「志津」と解する説もある。
古剣書においては、康和(1099)ごろの大和の定生を薙刀の創始者とする説が多い。康和(1100)に初めて造った、としたものさえある。大和の定秀を創始者とする説があるが、これは定生の誤伝であろう。薙刀造りの上手としては、元暦(1184)ごろの伯州日照を初めとして、吉野期の但州法城寺国光、越前の金津権三国長、備前長船の義景、備中青江の吉次などの名があげられている。
「享保名物帳」にも、骨喰藤四郎、鯰尾藤四郎などの薙刀直しのほか、権藤鎮教薙刀が収蔵されている。江戸期になると、堀川国広・河内守国助・津田助広・粟田口忠綱・相模守政常・水心子正秀・大慶直胤などの名工が、やはり薙刀の名作をのこしている。
薙刀術に巴流や静流があった。巴流は芸州広島藩で行われていたが、巴御前に仮托したものである。木曾義仲の家に「竜王作の長刀」が伝来していたことは、軍記物に見えているが、巴御前が薙刀をふるって奮戦したことは、軍記物にも見当たらない。
静流は奥州仙台藩では静流京師伝、播州三草藩では志津賀流または賤が流と称していた。静流は天正3年(1575)、長篠の役で討死した望月相模守定朝が、聖徳太子の兵法の奥義をさとって開いたとも、源義経が鞍馬山で体得したとも、この流派では志津三郎兼氏作の薙刀ばかり用いたからともいうが、いずれも後世に付会である。薙刀は戦場において、馬上ならば十徳、徒歩ならば九徳あるというが、その内容は明らかでない。
(参考文献:日本刀大百科事典より転載・引用・抜粋)